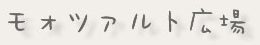モーツァルト一考・代表 加藤明のコラム(K618)
モーツァルトはわずか35年余の生涯で800曲に及ぶ極上の作品を後世に残してくれた。
今日ではその800曲ほどの殆どが何らかの音源で入手できるといわれている。この一点だけとっても、私たちはかつて体験したことのない豊穣なモーツァルト鑑賞環境によくしていることになる。
私は専らモーツァルトをCDで楽しんでいるが、過日ふとしたことから自分のCDの棚卸をこころみた。その結果、曲目にして焼く600曲ほど在庫していたから、20数曲はまだ手に入っていない勘定であった(旧KNoで)
私はコレクターにはなれないが、音源としてまだ耳にしていない曲が他に存在するということだけで「まだまだ死ねないッ!」とつい力んででしまうからひょっとしたモーツァルトは寿命延長にも効能があるかもしれない。
私の場合、さあオサラバの時が来た、と悟って今生のなごり、全曲鑑賞キャンペーンを実施するとして、K1から順に全曲聴き終わるまでざっと2ヶ月くらいかかる計算であった。いのち根性のきたない私のこと、最終のK626レクイエムまできたら、やれランドン盤となんくせをつけて一分、一秒でも長引かせ、セコクこの世に未練を残すことになるだろう。
それはさておき、600曲余のモーツァルト作品全体を振り返り、鳥瞰すると改めてその豊かな多様性に感嘆する。長は3時間半を要するオペラから短は1分に満たないカノンまで様式・形式の異なる一曲、一曲がまぎれもなくモーツァルトを主張して憚らないのだ。
そしてまた、モーツァルトはなんと多くの曲を他人(ヒト)のために書き贈ったことだろう!とつくづく感じ入ってしまうのだ。○○伯爵夫人のために、弟子の○○嬢の演奏会用に、お世話になった貴族の○○のために、友人の○○のために、etc。当然のことながらウィーンで独立した1781年以降、このヒトのための曲作りは一層顕著になる。(因みに、私の会員番号K618「アヴェ・ヴェルム・コルプス」は妻コンスタンツェが湯治場バーデンでお世話になった友人の合唱指揮者アントン・シェトルのために作られた)
このような利他的なモーツァルトの姿勢はどこからきているのだろうか?色々な推測が出来ると思うが、究極のところ私はここにモーツァルトのヒトビトに対する明るく、素直で屈託のない性格が反映されているのではないか、と考える。
そして、モーツァルトはヒトとの関わり方においていつも真摯であるばかりではなく、一流の折衝力を持っていたように思われる。つまりヒトには素直に自分にさらけ出す一方、きっちりとお相手からも知的・物的栄養素を頂戴するといったギブ&テイクの法則を実践していたようなのだ(かつて小林秀雄がモーツァルトを評して「歩き方の達人」と語ったことが思い出される)
さて、しかし、私たちはこのようなモーツァルトの性格傾向は厳父レオポルトおとびレオポルトの教えとは全く異なるものであることを知っておく必要がある。
何せレオポルトときたら、息子がパリ・マンハイムに就職旅行に母を伴って出かけた際、わざわざ旅先に手紙をしてため次のように忠告する親であった。いわく「息子よ、おまえに無償で尽くしてくれる友人が千人の中に一人でもいたとすれば、それはこの世の奇蹟の一つだ」と。
私はこのレオポルトの忠告が意味する過激な人間不信の響きに驚き、慄然とする。息子とはいえ、20歳を過ぎた青年に放つ言葉として尋常ではない。
生涯報われない副楽長停まりの自分の境遇が言わしめたものなのか、それはともかく、このようなレオポルトの偏狭な人間観がついに息子を説得することはなかった。それどころか、このパリ・マンハイムの旅を境にモーツァルトは実在する自我に目覚め始め、自らの意思で新しい世界へ一歩一歩踏み込んでいくことになるのだ。実在する自我とは「自らを選択する自我」のことだと大好きなJ・P・サルトルが言っていたが、1781年5月にコロレード大司教と決別し、ウィーンに住み着くはるか以前に息子は父レオポルトから開放されていたのだった。
ところでサルトルがモーツァルトを評して「モーツァルトはどんな場合でも農民の手の届かないところにいたことはなかった」と遠まわしながらその本質に触れていたことを蛇足ながら記しておこう。
そのような父レオポルトは1787年5月28日ザルツブルクで世を去っているが(享年67歳)この1787年の正に5月から6月にかけて、なぜかモーツァルトは立て続けに6曲のリート(歌曲)を書いている。しかもこの6曲は30数曲あるモーツァルトのリートの中でも、きわだった名曲に属するものである。(1785年意有名なゲーテの詩による「すみれ」という忘れられない傑作もあるが)
その中でも「ラウラ」に寄せる夕べの想いと「別れの歌」の美しさは別格だが、以下にこの6曲を整理してみよう。
- 老婆 K517(ハーゲドルン) 1787年5月18日作曲
- ひめごと K518(ヴァイセ) 1787年5月20日作曲
- 別れの歌 K519(シュミット) 1787年5月23日作曲
- ルイーゼが不実な恋人の手紙を焼いたとき K520(バウムベルク) 1787年5月26日作曲
- ラウラに寄せる夕べの想い K523(カンペ) 1787年6月24日作曲
- クローエに K524(ヤコービ) 1787年6月24日作曲
ご覧の通り、以下にこの6曲が集中した形でかかれているかがお分かり頂けると思う。
さらに注目すべきは、これらの作品群に前後して連連と傑出した作品が産み出された事実である。K515およびK516の弦楽五重奏曲、K521四手のためのソナタ ハ長調、K522音楽の冗談、K526ヴァイオリン・ソナタ イ長調、そしてK527のドンジョバンニと綺羅星のごとく傑作が並ぶのだ。
音楽的なスケールから見て、この6曲のリートはドンジョバンニを頂点とした対極群の隙間にひっそりと咲いた、いわばスミレのような花びらの塊といった趣がある。きらりと光る生命感あふれる花、その情澄感、寂寥感ゆえに私たちを魅了して止まらない花のかたまりであり、とても素通りできない。誰しもが一度は立ち止まり、真剣に聞き入ってしまうモーツァルトならでは、のモノローグが秘められていると思うのだが。
レオポルトの死と期を同じくしたモーツァルトのリートの世界。一曲、一曲に込められたパロールの陰影の深さはモーツァルトの偏狭ではあっても愛すべき父への心からの哀悼表現だったかもしれない。この6曲の集中的なリートの意味するもの。私の中では父レオポルトししてその死と切り離して考えられないのである。