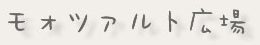モーツァルト一考・代表 加藤明のコラム(K618)
その日はめずらしく文字通りの五月晴れでした。新聞少年(18歳は青年かな?)の早い朝の配達から解放され、まどろんだ雰囲気そのままに、気の合う仲間数人が自由が丘・東横線駅にほど近いこじんまりした神社の境内に散歩ついでに立ち寄った時のことです。かねて私たち毎日新聞自由が丘専売所の仲間から慕われていた専業さん(アルバイトではなく、集金や拡張業務も担うプロの職員)であるマツダさんに私はヒョイと呼び止められました(フルネームはわからないまま、みんながマツダさんと呼んでいました)
マツダさんはそのときなぜかテープデッキを片手にし、赤い大きな耳にはイヤホーンを着けておりました。突然の呼び止めに一瞬どうしたのかと不安気な反応の私に、持ち前の人を包み込むニコニコまん丸素朴そのもののマツダさん、やおら自分のイヤホーンを取り外し、「加藤くん ホラッ リンツだよ」というなり、私の耳にイヤホーンを押し当てたのです。
そのとき、私の脳髄に響いたリンツ(ハ長調・K425)は以前に故郷の下宿先で独り聴いたリンツとは全く異質なものでした。指揮者が違うとか、オーケストラがはじめてということからの異質さではなく、それはそばにマツダさんがいるリンツということからくる異質さだったと思います。第一楽章アダージョの憂いすら感じさせる重々しい序章に続き、一転して若々しく、イキイキ感いっぱいのテーマに移ったあたりからイヤホーンに流れたこのリンツ。いわばこの劇的なリンツに聴きほれた私は、結局そのあと第4楽章までずっとこのイヤホーンを独り締めしてしまったのでした。
この事件(私にとっては大事件でした)をきっかけとしてマツダさんという専業さんは私にとって、単なるニコニコまん丸赤ら顔の先輩から、心底信頼を寄せる兄貴に成り変わったのでした。
自由が丘でのこのリンツ体験は私にとって、モーツァルトのすごさを再発見させる出来事ではありましたが、それ以上にマツダ兄その人の不思議さを深く印象付けるものとなりました。
私には、それまでのマツダ兄は周囲の見方と同様、毎朝誰よりも早く起き、私たちの倍以上の折込作業を鬼のような速さと正確さでやりこなし、他を圧倒する新聞配達業務員の鑑としてしか映ってなかったのですから。そんなマツダ兄がボーッとしていた私に突如リンツを聴かせ、私の心を揺振ったのです。早速私のマツダ兄研究が始まったのは言うまでもありません。
周囲の諸先輩にマツダ兄について取材したところ、マツダ兄は「某音大のピアノ科を卒業後、その道を志したが何らかの事情で夢を捨て、数年前から新聞販売店を転々としているちょっと変わった人」というのが共通した返答でした。さらに、出身地とか年齢とかの出自については誰一人まともにわかる人がいないという予想通りの不思議なマツダ兄だったのです。
東京に出て3ヶ月、この巨大都市には私の想像力の及ばない世界と人々がいる、ということをしみじみ感じさせたマツダ兄でした。そして不思議なことは、マツダ兄は自分の出自とか経歴といったことを他人に詮索させない独自のパワーを内包していたことでした。マツダ兄にとっては人が「どこの生まれで、どんな暮らしをしてきたか、どこの学校を卒業したか」という一般的に人の尺度や基準になるようなことがらはどうでもよいことであったらしいのです。
このような姿勢は私がそれまで植え付けられてきた価値観からは大きく異なるものでした。しかしこのような姿勢の方が何かしら健全で正しい人の見方のようで、無言のうちに人に対する視点や付き合い方を学んだような気持ちになったものでした。
自己の過去については一切封印しながらも周囲から敬意をもって認められ、独特な親和力をもったマツダ兄はいわば仏様のような人でした。そんな仏のごとき音楽のプロフェッショナルであればこそ、絶妙のタイミングで「ホラッ リンツ」と私にイヤホーンを預け、その後特別なことをしたようなそぶりは一切見せることがなかったのでしょう。
交響曲「リンツ」はその言葉の響きがとっても好ましいと思ってきました。ご承知のように、リンツはウィーンとモーツァルトの故郷ザルツブルグの中間に位置するドナウ川沿いに発展した工業都市ですが、日本語で呼びやすいし、何か耳障りがよい名称と感じてきました(かのブルックナー生誕の地としても知られていますが)。そんな「リンツ」はモーツァルトがウィーンで自立してはじめての交響曲であるばかりでなく、いわば交響曲の作曲者の情念が体系的に反映された最初期の作品であり、あとに続くロマン派をも予見させる名作と私は思ってきました(たとえばK183のト短調交響曲やK201イ長調交響曲との対比でみると明らかに人間的な広がりや情操的な豊かさが感じられるのではないでしょうか)
この頃のモーツァルト(1783年ですから27歳ころ)について、そしてこの「リンツ」の成立事情についてはここでは紙面の都合で触れることができませんが、私にはこの曲の凛々しくも端整な豊饒さは、その後オペラ作家として活躍することになるモーツァルトのいわば決意表明のようにも聞こえてくるのですが・・・。
(因みに当広場の特別会員三浦真君K527は正真正銘このリンツの市民です)
話をマツダ兄に戻します。前述の神社でのリンツ事件の後、マツダ兄は私にとって決定的な情報を伝えたのです(情報という言葉の意味が情に報いるということであるならば本物の情報でした)
それは渋谷にある「ライオン」という名曲喫茶の存在を紹介してくれたことでいた。この「ライオン」は誰一人として会話をすることのない、静寂さを常にたたえており、ひたすらにクラシック音楽を聴かせるために創られた、昔ながらの名曲喫茶の殿堂といったところでした。私は朝刊の配達を終えると代々木の予備校に行くことになっておりましたが、いつしかこの「ライオン」に途中下車しては夕刊の始まる時刻までバルトークやストラヴィンスキーなどを浴びるように聴くようになったのでした。
私はマツダ兄に感謝しました。その感謝の意味は単に「ライオン」を紹介してくれたことにとどまらず、「ライオン」に通いつめるようになって、自分の大学進学の望みがいかに希薄なものであったかを思い知ることができたということに起因します。職業に貴賤があるはずもなく、自分のやりたいこをを捜すのに大学に行かなければ捜せないわけでもあるまい。「ライオン」に通うにつれて、自然にこの青臭い発想が私の中に宿したのです。
こんな母の胎児的な心地よさを与えてくれた「ライオン」はマツダ兄から貰い受けた2度目のプレゼントであり、忘れることのできない置き土産となってしまいました。それというのも、その年の夏に我がマツダ兄はなぜか忽然と私の前から姿を消してしまったからでした。
確か7月の下旬だったと記憶していますが、いつもの通りまだ太陽が昇りきらない時刻に眠い目をこすりこすり2回から降りてきた私は、いつもと違う織り込み風景を目の前にしました。いつもの鬼のような速さと正確さで作業しているはずのマツダ兄に替わって、販売店のおやじさんが黙々と折り込み作業をやっていたのです。そばで作業していた仲間もその朝は無口で、今までにない緊張感が作業場をおおっていたのです。
尋常でないその空気はマツダ兄の突然の失踪を知らせていました。1年先輩のYさんに恐る恐る「マツダさんは?」と訪ねてみました。Y先輩は「マツダさん、上がってしまったらしいよ・・・」、とポツリ。上がる、とは業界用語でその店から突然いなくなることの隠語でした。
私はしばし突っ立ったまま呆然としている自分をどうすることもできなかった。そして、数日前、私にくれたマツダ兄の匂いの染み付いた黒のフランネルのセーターを想い出していました。そのマツダ兄が普段着ていたセーターが三つ目の、そして最後の置き土産になったことを自覚しました。
同時に「もう一生マツダ兄にはあえないんだ!」そのときの直感はするどく私をえぐりました。なぜならマツダ兄の凛とした生き方から推測して、後でのこのこ顔をみせるような野暮な人ではなかったからです。
さらになぜなら、自由が丘専売所の仲間全員が一端上がったマツダ兄が二度と戻ってくることがないことを完璧に受け入れていたからです。そして、驚くべきことは、このような突然の失踪にあっても、誰一人としてマツダ兄の悪口、陰口をたたかず、何事もなかったかのように粛々と暮らし始めたことでした。
以上がささやかな自由が丘における、新聞少年加藤の「リンツ」体験のあらましです。あれから35年の歳月が経ちました。今でも私のマツダ兄は仏様のように私の奥深いところで、ニコニコまん丸赤ら顔で行き続けているのです。
「加藤くん ホラッ リンツだよ」