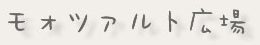モーツァルト一考・代表 加藤明のコラム(K618)
1787年5月28日、この日モーツァルトの厳父レオポルトがザルツブルクの「タンツマイスターハウス」で68歳の劇的な生涯を閉じました。当のモーツァルトは父の死に立ち会うことな
く(かの「ドンジョバンニ」の作曲に追われていたらしい)、姉のナンネル夫妻と長い間モーツァルト家に何かと尽くしてくれた友人で当地の神父、ブリンガーの三人が看取りました。このレオポルトの死の一ヶ月ほど前に、モーツァルトは父に最後の手紙を書き送っています。感動的で美しい文章です。音楽の虫モーツァルトの当時の演奏家へのシニカルな批判はこの手紙でも健在ですが、注目すべきはかってパリ滞在中に母マリーア・アンナを喪ったとき、22歳のモーツァルトが父にあてた手紙の一説「死はぼくらの人生の真の最終目標」というあの死生観がここでも繰り返されている、という事実です。
「死はぼくらの人生の真の最終目標ですから、ぼくはこの数年来、この人間の真の最上の友とすっかり慣れ親しんでしまいました。その結果、死の姿はいつのまにかぼくには少しも恐ろしくなくなったばかりか、大いに心を安め、慰めてくれるものとなりました!
そして、死こそぼくらの真の幸福の鍵だと知る機会をあたえてくれたことを神に感謝しています。ぼくは(まだ若いとはいえ)ひょっとしたらあすはもうこの世にはいないかもしれないと考えずに床につくことはありません。でも、ぼくを知っている人はだれひとり、付き合っていて、ぼくが不機嫌だとか悲しげだとか言えないでしょう。そして、この仕合わせを毎日ぼくは創造主に感謝し、隣人のひとりひとりにもそれが与えられるよう心から祈っています。」(モーツァルト書簡全集Ⅵ、海老沢敏・高橋英郎訳)このような死生観がどのようにしてモーツァルトに宿るようになったかについては定かではありませんが、強いて関連づけられるものとして、当時出版されたモーゼス・メンデルスゾーンという哲学者(作曲家フェリックス・メンデルスゾーンの祖父)の著作「フェードン、あるいは魂の不死性について」(1767年)に書かれている死生観からの影響があるのでは、との見解が一部にあります。
メンデルスゾーンの影響の有無はともかくとして、当時の衛生環境からみて、現代とは比較にならないほど死というものが身近なものであった時代背景を無視することはできないと思われます。因みに、モーツァルトの兄弟は7人いましたが、そのうち7番目のモーツァルトと4番目の姉・ナンネル以外はすべて夭折しているし、モーツァルト自身の子供も6人生まれましたが、成人したのは2人だけでした。
このように、生存率の低い時代、薬効が乏しかった時代に想いを馳せるとモーツァルトのこういった死生観が宿るのも、むべなるかな、という感じがしてきます。私は今年7月に兄を病気で喪うというつらい体験をしました。私とは7歳の開きのある長兄ですが、父と同様の胃がんであっけなくあの世に逝ってしまい
ました。
兄は日本の敗戦間近に旧満州で生まれました。一年間の敗戦による抑留生活を経て、チチハルから父の郷里秋田まで母の手に引っ張られながら、42日に及ぶ生死をさまよう過酷な引き揚げ体験をしています(もっとも本人は断片的な記憶しかないようでしたが)。今年は戦後60年の節目の年ですが、兄は正に日本の節目の60年を全うしたカタチで他界したことになります。
社会への適応力とかビジネス感覚の面では欠点の多い性格でした。生き方は不器用でしたが、どこか憎めないものをもっている不思議なひとでした。この憎めなさというのは、きっと兄の徹底的に自分を誇らない姿勢からきていたのでは、と思っています。兄は自分に納得していない分だけ、ひたすら自分を探るようなところがありました。その読書量はかなり多く、絵やカメラの趣味をもち、一緒に山歩きをしてはそこらの草花を解説する、言ってみれば私の身近な師匠といった役まわりでした。誰よりも共有する情報量が多いことを兄と私は互いに承知しておりました。それが兄弟というものの特権かもしれませんが。
兄が日々兄でなくなっていく、という現実を健康体である私が平然と観察することほど奇妙で残酷な景色はありません。次第に私の位置が怪しくなりました。
兄は不平を一切言わない人でした。病院にも大昔から居るかのように馴染んでいる人でした。生きる望みを捨てない人でした。その激しい復活の意志は病院に見舞う私の悟りきった小さな復帰願望をはるかに超えたものでした。その復活の意志と裏腹に目の前で壊れていく兄。そのギャップが大きくなっていく容赦ない時間。私の手に余る兄の生きることへのしたたかな執念。人の執念に毅然として立ち向かうことの難しさ。
私は幾度も撃たれました。撃たれたあとには決まってこんどは涙が一気に噴出すのでした。こうして、私は徐徐に言葉を失っていきました。鋭い兄に見破られるのを覚悟で。しかし、兄は依然として饒舌です。見舞うたびに新聞の切り抜きで新刊図書の注文依頼があり、その本の内容についてコメントがありました。
こうした日々兄が兄でなくなっていく現実を前にして、私の脳裡をかすめたのが前述のモーツァルトの死生観だったという訳です。人生の真の最終目標たる死。モーツァルトの作品はそっちのけで、書簡に残した死生観が想い起こさというのはいかにも音楽には無縁の読書人の兄らしいのですが。兄との最後の対話はその死の11日前でした。その朝もいつもの通りに出勤前に病院に兄を見舞いました。
明らかに昨日までと様子が変わっていました。病室内に時間が流れていないのです。その真空のような静寂さは一切を拒絶する空気となって私をつつみました。(ダメダ、ニイサン、マダマダ、ガンバレ!)
ことばになりません。ベッドのそばで私は兄が私を見ていないことに気づき、恐怖をおぼえました。兄はあの時なにを見ていたのだろう。ベッドに座ったまま意識がもうろうとしている兄が不意に搾り出すような低い声でつぶやきました。
「アギラ…アド… エエヨ…アド……エエガラ……」。
「………」
聴き取れなかったふりをし、私は再度兄のそばに近寄り声をかけようとしました。
「………」
しかし、なぜか私は一言も発することができませんでした。全身が膠着していたのです。いや、魂までも。長い沈黙ののち、ひんやりとした兄の手をそっと握りました。そして、トボトボと真空の病室をあとにしました。
葬儀当日に私は半ば衝動的に《タカシを想うつぶやき》を綴りました。それは、病室でことばにならなかったことの
自責の念の顕れだと思います。私の「会報」の文章をいつも丁寧に評論してくれた兄はついぞモーツァルトを聴かぬまま逝ってしまいました。
この惜別の作文はいつかきっと兄がニヤニヤしながら、「これいいな!」と褒めてくれるはずだったモーツァルト、そのモーツァルト最晩年の白鳥の歌「クラリネット協奏曲」を背景としてイメージしています。文章を綴っているあいだ、特にそのアダージョに込められたモーツァルトのことばは兄と私のあいだに自然に溶け込んでくるのでした。兄と私を懐かしみ、結束させ、大らかに包み込んでくれるという点で、この曲は私たちにとって母のような存在なのかもしれません。
「死はぼくらの人生の真の最終目標」と語ったモーツァルト。彼はこの「白鳥の歌」を書きあげたわずか2ヶ月後、急ぐようにして最終目・・・
標に飛び立ちました。
《タカシを想うつぶやき》
もともと近くにはいなかったのだ
あの兄は
でも遠くからたくさん文がきて
引きずり込まれるように
おまえも遠くまで
熱い思いを届けた
兄と弟
近くて遠く
遠くて近い不思議
生き方を教えない
方法に無頓着な兄に
おまえは多くの手法を学んだ
おまえがなにものであるかの
たとえば
兄は音を嫌う
音の共有を赦さない
だからきまって
運転中おまえはじっとしている
じっとして兄が話し止むのをまつ
話し疲れた兄をかわして
ピアニッシモのモーツァルトをかける
ああおまえの周りに
こんな無礼な奴はいない
病に臥した兄と
一日を看護に費やす兄嫁と
それを見守る老いた母
ああいま兄に聞こえることばはなにか
ああいま兄にどんな音が棲んでいるのか
ところで
いままでいいことあったんだろうか
いいことってなに
ひっかかる
「いままでいいことあったかい?」
求めてきたはずのいいことは
つかんだヒトの話では
おおむね虚しいとさ
きっといいことというのは
おまえからすり抜ける慣わしで
でも兄よ
「いままでいいことあったかい?」
老いた母がひん曲がった腰を
まっすぐにすると
おまえの世界が一瞬にして
振り出しに戻る
臥した兄をながめる母
「ヨイショ!」と立ちあがる母に
涙するおまえが
まだそこに居た
考えてみると
おまえはいつも自分の居場所をさがしてきた
兄の最期とむきあっても
居場所さがしはつづいた
おまえの兄とはなにか
兄のげんじつ
弟のフィクション
兄の遠くをみる眼
その先にある弟のあせり
おまえはいつも
そしてもしかして兄も
自分のありかをたずねていた
みんなにあって兄になかったもの
家族への偏愛
兄にあってみんなになかったもの
父母との宿命的な葛藤
みんなにできて兄にできなかったこと
それは
おもねるという処世術
兄ができてみんなができなかったこと
それは
おまえに片栗の花をおしえ
その秘められた思い出を自慢したこと
「片栗の花は死んだ親父が小さい頃おしえてくれたんだ」
グッドバイ
遠くて近い兄