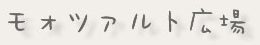モーツァルト一考・代表 加藤明のコラム(K618)
相変わらずモーツァルト漬けの生活が続いている。
モーツァルト漬けとはモーツァルトを聴き続けることであり、いまにモーツァルトを蘇えらせている、といった意味である。
モーツァルトを蘇えらせる、ということは私のことばでモーツァルトを考えることであり、小林秀雄流に言えばそれは日本人である私が日本語でモーツァルトを考えることであり、私なりのモーツァルトの歴史を生きることである。
このことは、数百万人のモーツァルトファン(モーツァルトを鑑賞する人)がいるとしたらそれだけのモーツァルト像があり、私は数百万人分の一のモーツァルト像をもつ日本人ということを意味している。
すべての芸術家に照らしても同様のことが言えるが、このような個々の鑑賞する側の観点とか姿勢についてもっと叫ばれてよいのでは、と感ずることがある。
生誕250年にあたる今年はさまざまなメディアを通じてモーツァルトが世間を賑わしている。
そして、洪水のごとき情報の氾濫に多くの聴き手はちょっとした麻痺状態を呈している。
W.A.モーツァルトが1756年1月27日にザルツブルクに生を享けた、という歴史的事実によって、ただそれだけで。
だから、どうしたというのだろう。
そのことが、どれだけモーツァルトを考えることにつながっているだろう。
私にとってモーツァルトは依然として深い謎だ。
そのモーツァルトがこれ見よがしに祭り上げられているのを傍観(または諦観)しつつ、さらにその謎が深まるのを禁じえない。
かつて小林秀雄が「言う人は知らず、知る人は言わず」と皮肉ったきょうびの現象にいささか私は嫌気がさしている。
「モーツァルトってどんな人?」という関係性を刺激する風潮をつくったのは生誕250年祭を声高に標榜する多くのマスメディアに違いない。
好意的に考えると、この現象はモーツァルトを音楽的に普及させるという点で大変喜ばしいことだ。
ビギナーに、「じゃ聴いてみよう」という意思を触発し、歓迎する環境が整うことになるからだ。
反面、たとえば「5歳でピアノ曲をつくった天才」といったメディアが好んで吹聴する手垢のついた形容が、ともすると音楽とは関係ないところでモーツァルト像の歪みをもたらせていると感ずるのは私だけだろうか。
もし、その音楽を真っ向から聴くことなく、断片的な特徴やイメージを弄ぶだけの生誕250年祭だとしたら・・(朝のモーツァルトなどと間違ったパック商法が横行している)。
私の体験ではモーツァルトを飽くことなく聴き続けることでしか、これほどの巨人を自分なりの尺度やことばで考え語ることはできない。
磨くべきは武器としての耳なのだ。
鍛錬すべきはモーツァルトに向き合う虚心な姿勢なのだ。
聴いて、聴いて、聴き分けることなのだ、モーツァルトの言葉としての音楽を。
たとえば、モーツァルトが10歳のころオランダ滞在中に書き表した「ガリマティアス・ムジクム」K32を聴く(ガリマティアスとは混成曲といった意味)。
そこには貴族の食卓音楽の域をはるかに超えたもの、音楽としての機知に富んだモーツァルトならではのメッセージがつまっており、聴くもの(私)を魅了してやまない。
たとえば、4曲ある「リタニア」のなかのK243・変ホ長調は数あるザルツブルク時代の教会音楽のなかでもその深遠さと曲想の豊かさにおいて群をぬいており、もっと広く知られていい傑作に違いない。
たとえば、反対に広く知られている「魔笛」のパミーナとパパゲーノの愛の二重奏。
この一曲だけでもモーツァルトの真髄を垣間見ることもできるのだが、ここにモーツァルトらしさのひとつの象徴を見出すのに私は情けなくなるほど長い年月をかけてきたことを告白しなければならない。
かつて久元祐子女史がいみじくも「モーツァルトは捕まえたと思った途端スルッと手からすり抜ける神秘性がある」と語っていたが、捕まえたと思うまでの修練がどれほど険しいものであるかに気づく必要があろう。
そこには、芸術家(ピアニスト)が芸術家(作曲家)に迫る姿が聴く者、視る者を圧倒する理由が潜んでいるし、われわれを感動せしめる源泉が確かにあるのだ。
だから、安易に解ったとは言うまい、思うまい。
やはり残るのは深い謎。
それでも私はモーツァルトを聴き、語り、接近を怠らないだろう。
なぜか。
今のところ、モーツァルトが好きだから、という以外に返答が浮かばない。
そのほかのいかなる論理も寄せ付けないところに、私のモーツァルトがいるらしい。
さて、私たちが主催した発足10周年記念コンサートがモーツァルト生誕250年祭と重ねあうかたちでアトリオン音楽ホールにおいて1月29日に開催されたことは記憶に新しい。
このアニバーサリーコンサートに600名を超えるモーツァルトファンが駆けつけてくれたことは主催者として望外の喜びとなったのはいうまでもない。
アンサンブルは個々の技量の高さをキッチリと発揮したし、指揮の村上満志氏はモーツァルトテンポを見事に体現し、会場をモーツァルトモードに包み込むことに成功した。
しかし、それ以上に私を興奮させたのは何といっても久元祐子、菅原潤、長谷川留美子
ソリスト三氏を中心とした演奏の質の高さであった。
秋田が生んだプリマドンナ長谷川女史のドンナ・エルヴィラはベテランらしいステージパフォーマンスでみごとにドンナ・エルヴィラの複雑な心情を歌いあげたて秀逸であった。
フルートの菅原氏は「モォツァルト広場」に初登場であるにもかかわらず、私たちの流儀をすばやく洞察され、諸準備などつたない運営に対しても不平ひとつ漏らさず最後までコンサートを盛り立てて下さった。
秋田市のご出身ということでフルートコンチェルトK314ではその第2楽章のカデンツァに「秀麗無比なる鳥海山」の県民歌をフィーチャーするというサプライズサービスで館内全体のオーラを巻き起こした。
これは正に音による一体感を呼び起こす技であり、秋田にモーツァルト降臨の一瞬であったと思う。
久元女史の鍛え抜かれた技巧とその解釈が冴え渡った「戴冠式コンチェルト」は見事にオーケストラを掌握しながら、モーツァルト晩年の枯淡と清澄と明朗感をつむぎだし、深い感動で会場を包み込んだものである。
それは秋田における250年祭コンサートの締めくくりにふさわしいモーツァルトの至福感の体現であり、深く刷り込まれる忘れがたい名演であった。
このアニバーサリーコンサート実現にあたり、モォツァルト広場の幹事諸兄のみならず多くの会員の方々に使命感とも言えるご協力をいただいたことは、私にとって生涯の宝を得たような感激として残っている。
この生涯の宝・仲間を得た手ごたえこそはW.A.モーツァルトが私にくれた生誕250年祭の回答なのかもしれない。
とまれ、コンサート終了後多くの余韻に包まれた笑顔に触れたときに、冷や汗をかきながらホッと胸を撫でおろす広場の代表がいたことを記してペンを置こう。
【推薦曲と推薦盤】
今回は10周年記念コンサートの全プログラムとその演奏を推薦します。