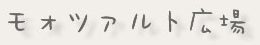モーツァルト一考・代表 加藤明のコラム(K618)
「モォツァルト広場」には現時点で130名を超す会員が登録されている。
会員の平均年齢はざっと50歳代も後半という比較的熟年層の集いといえよう。
つまり、明らかにモーツァルトの35年間の実人生をはるかに超えた年齢の人たちが今もって嬉々としてモーツァルトを楽しんでいる、ということになる。
そればかりではない、筆者のように、40歳(孔子に言わせれば不惑の年齢)を過ぎて、ようやく探し当てた宝物のように驚きをもってモーツァルトを迎える輩までいるが、そのことがそれほど特別な現象でもないようなのだ。
論語の説く年齢の秘密からすると、モーツァルトは「三十にして立つ」という正に自立する年代の道半ばにして昇天したことになる。
その後の惑うことなき四十代や天命を知る五十代を体験することもなく、である。
十有五にして学(楽!)を志して、三十にして立った(絶った!)モーツァルトに不惑を過ぎ天命を知る人たち、それどころか耳順うくらいの歳を重ねた人たちまでが人生を懐かしむように聴きほれているという、考えてみると皮肉で面白い現象が確かにある。
この奇妙さはモーツァルトのモーツァルトたる所以だと識者は言いそうだし、それが彼の芸術の深さだ、と賢しらに指摘されそうでもある。
この際、私はこう考えてみた。
きっとモーツァルトは孔子の謳った年齢観の枠から外れるほど異例のスピードで人生を突っ走ったのではないか、と。
時熟という言葉で人間の年功を表現した哲学者がいたようであるが、モーツァルトはその時塾の速さにこそ天才性をみるべきなのかもしれない。
たとえば、学を志す15歳はモーツァルトにあっては5歳のナンネルの楽譜帳以来はじまっており、パリ・マンハイムの就職旅行を経て自立を確信し、ウィーンに躍り出た25歳ではすでに惑うことなく自らの進むべき道を開拓邁進した、といった具合に。
とすると、モーツァルトはいつの時点で天命を知ったのだろう。
1787年5月、父レオポルトの死に及んで「死は私の真の目標」と語ったあの時点から天命を意識したのだろうか。
いかにもこのレオポルトの死後残された4年半の余命をモーツァルトは天が彼に与えた使命を自覚し孤軍奮闘することで全うしたかのようにみえるが。
願わくは、耳順(みみしたがう)60歳のモーツァルトを聴いてみたかった、と思う昨今である。
▼ ▼
どこかの社会学者が「現代人が生まれて死ぬまでに果たして何人のヒトと知り合いという関係をもつか」という推論で、無論個人差のはげしいことではあるがと前置きしつつ、約2,000人という数字を当てていたことを思い出した。
もうすぐ還暦を迎える私もこの数字をあてて振り返ってみると、「ずいぶん多くのヒトの世話になっているもんだ、世話になってきたもんだ」という感慨をもってしまう。
因みに、我がW.A.モーツァルトについていうと、1991年に東京書籍より出版された《モーツァルト事典》には関連人名事典として約1,200人の索引名が載っていた(もっとも直接モーツァルトと接点のあろう筈のないハスキルとかカール・バルトなどもはいっているが)。
モーツァルトの35年と10ヶ月の生涯というのは、現代の私たちからみれば大変短いものではあるが、当時の音楽家の平均的な他人との接触数と比較するとはるかに多かったのではないかと思われる。
ご承知のように生涯の3分の1にあたる約10年を旅で過ごしたことからも窺うことができる(旅先での多くの知己を得てモーツァルトは成長してきた)。
増してや、ザルツブルクを逃れウィーンで独立独歩の道を選んだモーツァルトであれば、できるだけ多くの弟子をとり、音楽会を開いてくれる貴族へ営業をかけ、写譜屋との交渉を日常的にやっていかなくては暮らしていけなかった筈だから。
▼ ▼
ところで、猛烈なスピードで人生を駆け抜けたモーツァルトに果たして先生と呼べるヒトが何人いたものだろうか、と考えてみた。
ここで私が言うところの先生とは、自分の生き方に影響を与える、とか自己の人間的な成熟のために道筋を示してくれる師匠といった意味合いであり、端に音楽上の教育指導者とか規格と標準を教える学校の先生という意味合いではない(ご承知のようにモーツァルトはただの一度も学校教育というものを受けていない)。
ヒトの一生のうちにはその成長プロセスに応じた先生が何らかのかたちで存在するもの
らしい(ほとんどの場合「よい先生」は自らを先生と認識できないもののようであるが・・・・)。
中でも思春期、青年期における先生はその人のその後の人生に決定的な意味をもたらすケースが多く見受けられることは異論のないところと思う。
ではモーツァルトにあって決定的な先生は誰なのだろう?
この設問で思い巡らしてみたが、どうもそれは父レオポルト・モーツァルトその人以外に生涯の師匠といえる人物は見当たらないように思うのだ。
他ならぬレオポルトをロールモデルとしてウォルフガングは自立しえた、といっても良さそうなのである。
ロンドンのクリスチャン・バッハ、イタリアのマルティーニ神父やウィーンでのスヴィーテン男爵など音楽の師であり、敬愛する協力者は確かにいたが、先生という意味あいとは少し違っていたようだ。
今日われわれは残された親子の書簡から、成長進化していくモーツァルトとその息子に
どこまでも父親としての訓えを施そうとするレオポルトの頑なな姿勢を感じとることができるし、自立しようとするモーツァルトが父に反論しつつも深い畏敬の念を抱きつづけたことがうかがい知れるのである。
モーツァルトは生涯父レオポルトが指し示した人としての道、その呪縛とも言える道に真剣に向き合い、呼応しながら生きたといっていいのではないだろうか。
プラトンはソクラテスが「教育の目的とするところは自己教育に他ならないし、少なくとも自己教育に気づかせることだ」と説かれた、と伝えている。
私はこのソクラテスの言に、モーツァルトの実存性、したたかな独立独歩の生き様を重ねることができるように思う。
モーツァルトが誰にも依存せず、本質的に寄る辺のない自己を見つめ、生活者であることの切実さを強く意識しながら、数々の普遍的で宇宙的な傑作を残した背景に激しい自己教育と自己鍛錬の信念があった(K515、K516のクィンテットはその頂点と言えまいか)。
自己鍛錬のみが生み出す創作という生きる希望があった。
この啓蒙時代の音楽家は誰の真似をも即座にモノにし、同時に誰もが到達できない領域を次々と切り拓いていったが、その原動力こそ自己教育(鍛錬)であったことに疑いの余地はない。
この弛まぬ自己教育の険しい道こそ、実は父レオポルトが20年に及ぶ親子での二人三脚の生活を通して、自ら指し示した親としての訓えであったと思う。
だから、父の意に反してウィーンで自立することになる息子にレオポルトは自分の生き様を投影したに違いない(レオポルトも長男でありながら故郷アウグスブルクを棄て、逃れるようにザルツブルクに来たことを忘れまい)。
ご承知の如く、1781年にウィーンとザルツブルクのはざまで天才親子は激しく衝突するが、その激しさの刻印はその後のモーツァルトの自立を保障して余りあるほど酷なものであったのだ(事実、この事件以後W・A・モーツァルトはザルツブルクの市民権を抹消されている)。
ここでは、自己教育に目覚めた子供は親との迎合や親へのおもねりを好まないものだ、という特性に改めて思い至ったことを記しておきたい。
▼ ▼
再度、自らにレオポルトのような先生がいたか、と問うてみた。
答えは言うまい。
胸に閉まっておこう。
しかし、このモーツァルトへの設問が無意味でないことだけは宣言したい気分なのだ。
レオポルトはウォルガングの才能を発見したその瞬間、「神が私に授けた宝」と悟った。
これは恐ろしく正しい判断なのだ。
この直覚力の高さがモーツァルトをモーツァルトたらしめた根底の理由であることに、
気づくことが必要に思う。
自分の子ではなく、神の申し子と認識するに至ったからこそ幾多の危険を顧みずヨーロッパ中を旅しながら教育した、といっていい。
貧乏音楽一家のどさ回りとか興行的な目的の旅行といった表面的な捉え方に流されず、レオポルトの旅の先々でのワクワク、ドキドキ、ハラハラを想像してみよう。
共に想い起してみようではないか。
なんなら一緒にマリア・テレジアの前に立ってみよう。
この世にこれほどの育て甲斐のある子供がいるものだろうか。
レオポルトと息子が歩んだ当時としては常軌を逸した離れ業の如き師弟関係を想い起し、二人の創った音楽を聴き、楽しみ、驚き、決してこの親子の歩み(それは言い換えれば二人が選んだ人生なのだが)を見失わないようにしたいと思うこのごろである。
レオポルトがウォルフガングにどういう教育をしたか、については一般に知られている。
個人レッスンはもとより、幼いころから国外への旅を実行し、旅の先々での音楽レッスンもまめに受けさせるなど当時としては異例の教育カリキュラム(?)を施した。
もちろんウォルフガングの天才性を見抜いたからこその、とてもリスキーな旅の連続ではあった。
【推薦曲と推薦盤】
☆ 弦楽四重奏曲 K465 ハ長調 「不協和音」
本文にもある通り、1781年5月モーツァルトはウィーン定住を決意した。それは父レオポルトの意に反した事実上の独立宣言であった。このときのレオポルトの焦燥と憤りと不安といった心情は底知れないものがあった筈だ。
この訣別を経て4年後の1785年の2月にレオポルトがウィーンを訪れ、2ヶ月ほど滞在した。
これを最後に二度と二人がこの世で会うことはないのだが、レオポルトのウィーン訪問はモーツァルト親子のかつての激しい衝突による空白を埋めるに充分なほど二人にとって感動的で意義深いものとなった。
その意味で、K466・ニ短調のピアノ協奏曲、そしてK458・K464・K465と連なるいわゆる「ハイドンセット」と称する弦楽四重奏曲こそはモーツァルト親子がウィーンでの成功を祝った記念碑的な傑作群と言えよう。
ここでは全部で6曲の「ハイドンセット」のうち締めくくりのK465・ハ長調「不協和音」の推薦盤を記述する。
- ハーゲン四重奏団(2001年) 演奏約31分 471−024−2 グラモフォン
第一楽章のいわゆる不協和音で書かれている序奏部のアダージョが私のもっている中ではもっとも遅いのが特徴。この沁みるような内省感がたまらなくいい。
2)アマデウスSQ(1966年) 約24分 423−300−2 グラモフォン
独特な気品が漂うこの曲の代表格。ハーゲンが遅いのか、アマデウスが速いのか。
3)ズスケSQ(1974年) 約30分 0002732 CCC
一時ズスケから離れられなくなりました。威厳と親和の融合が醸し出す愉悦のときから。
3)ジュリアードSQ(1977年) 約31分 SICC434−6 ソニー
4)イタリアSQ(1966年)約31分 462−262−2 フィリップス
5)スメタナSQ(1975年)約26分 COCO−75540 デノン
6)アルバン・ベルクSQ(1989年)約29分 TOCE−9003 東芝EMI