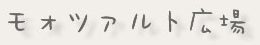会報より
モーツァルト雑感 会員番号 K576 倉田直樹
自分らしく生きる、という言葉を、ふだんわれわれは特別の抵抗もなく、むしろ耳には心地よい処世訓のひとつとして簡単に受け入れてしまうことが多いように思われるけれども、現実に自分らしく生きることができるのは、われわれのなかでもごく少数の恵まれたひとびとや、あるいはモーツァルトのようなひと握りの天才にのみ許されることかもしれない。
交響曲第25番は初期の傑作とされている。録音当時71歳であった巨匠、クレンペラー指揮によるディスクを聴くと、めまぐるしい早さのテンポには失笑を禁じ得ないし、若きモーツァルトの意気込みを、悪意をもってデフォルメしたかのような印象すら受ける。他の作曲家の指揮では緩慢の代名詞のように指さされるこの巨匠を駆りたてたものは何なのか。老人は、17歳のモーツァルトの自我のかわきや焦燥感を、高所から見物客として楽しむことに飽きたらず、少年の目線に降りて、熱狂する踊り手としての立場を選んだのだろうか。優美さや気高さ、倫理観は排除され、神童の肉声がとぎれなく増幅されていく。調和などという、のろまで野暮な概念は捨て去られ、足ばやに、絶対の自由と、みさかいなくおのれを主張する奇怪なエネルギーが、くっきりとあとに残された。
自分の個性を伸ばせ、自分らしさを大切にしろ、自分の心に正直になれという。自分らしく生きろと、したり顔で新聞やテレビは日々連呼する。自覚をうながされた自分はどんどん数を増し、膨張するばかりである。しかし冷静に考えれば、そもそも自分などというものは醜悪のかたまりではないのか。いま、17歳は恐怖の対象である。その年頃の少年にどれだけの自我が確立されているのかは疑問だが、自分らしく生きようとただそれだけを思うあまり、しかし肝心の自分そのものが限りなく悪で埋めつくされているならば、周囲の一切をかえりみる必要も感じず、ひたすら悪の快楽を追い求めることにもなるのではないか。最近の少年犯罪を見聞きするたびにそんなことを思う。
モーツァルトは、その短い生涯の3分の1が旅であったという。肉親や庇護者との確執、貧困等、実生活では束縛の多い人生であったことが知られている。17歳の交響曲第25番で高らかに自己宣言し、翌18歳の第29番ですでに完璧な美をつくりあげたおまえは、自分らしく生きることができたのかと、後世の人間がたずねたら、どういう答えが返ってくるだろうか。自分がなにほどのものぞ、とただ笑われるだけかもしれない。「悲しみの強さはわかるがその原因はわからない」。『コレクター』『魔術師』などで知られるイギリスの作家、ジョン・ファウルズはモーツァルトについて語ることの難しさをこのように評した。無理解と不自由さにとり囲まれながら、天才はすべての音に自分らしさの刻印を焼きつけた。