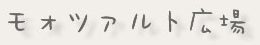会報より
あなたにとって、あるいは、私自身の中に存るモーツァルト 会員番号 K309 杉田明浩
私達が、ふとした会話などの中に「モーツァルト」という言葉がささやかれるとき、一種、心のざわめきがおこるのは、多少なりともモーツァルトの人となり、音楽となりを知っている人、それでなくとも「ああ、学校で教わったナ」とか、「うん、アマデウス、あれは良かった」などなど、枚挙にいとまがない、とは、こんなことを指して云うのだなと私などは思うのですが、皆様は、如何でしょうか。
モーツァルトという人物に、「人物」として、「常識」という物差しなり定規なりが用意されると、おそらく、「非常識、極まりない」という言葉が、待ってましたとばかり飛びかかってくるのではないか、という想いが、昔学校で、理科実験室でかえるを解剖したら、腸がにょろにょろでてきたという、「発見」の思い出よりも、驚きが少ないともかぎりません。
そんな、「非常識人間」モーツァルトを万人が(私を含めて)時代を超えて、愛するのは、彼の「音楽」が素晴らしい、とは月並みな表現ですが、この、心のひだをくすぐる、あるいはセンチメントな、彼の「音楽」は、まさに我々には、極上のワインを心のオアシスに味わうことの出来る、他の作曲家とは別の、独特の愉しみを与えてくれているように思うのです。
私もまた、ささやかな、モーツァルティアンな、わけですが、学生時代、仲間同志で行った、(今はなき)秋田市の某喫茶店で、「ここのココア、おいしいのよネ」と憧れの先輩が、オーダーすると「じゃ、ボクもお願いします」と私。
マスターは、我々がクラシック関係の人間と知ると、かけてくれたLPが、我らがモーツァルト晩年の最高傑作の1つ、クラリネットコンチェルトでありました。
私は、5才でピアノを始め、ご多分にもれず、最初のモーツァルト初体験は、ソナタハ長調K.545。高校生の頃は、レコード屋で、「よし、クラシックはこのLPから」と買ったのは、クーベリック・バイエルン放送響の「ハフナー」「リンツ」でありました。
その頃は、「リンツ」の躍動感に親しみをおぼえましたが、そうこうしている間に、「ハフナー」のセレナードの哀感も、なんとなく、味わえるようにもなりましたね。
いつの日か、会員番号K.309のソナタを弾きこなせる日がくるのを夢見て、私、作文を終わらせていただきます。
平成12年10月9日(月)
自宅教室にて 明浩