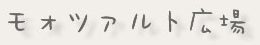会報より
ドン・ジョバンニの数世紀・・・会員番号 K332 片岡 元
スガナレル 「あれ、だんなさま、これこそ神のお言葉です、だんなさまに
授けられたお訓しです。」
ドン・ジュアン 「神がおれに訓戒を与えるのだったら、もっとはっきりしゃべ
るがいい、おれに聞かせるつもりがあるのなら。」
いやしくもモォツァルト広場の末席を汚すものとして、いつかはしかるべき水準のオペラのライヴを聞きたいというのは、筆者数年来の希望であった。チャンスは訪れるもので、この執着心と来日する名門歌劇場の公演日程とのマッチングにより先日いきなり夢がかなってしまった。そこで、感動さめやらぬうちにとそれにちなんだ雑文を寄稿させていただいた。
観劇したのは、ドン・ジョバンニ。いうまでもなくモ−ツァルトのオペラの中でも傑作の一つであり、筆者はこれまでTV放送やDVDなどで楽しんでいたのだが、このたびやっとライブで観ることがかなった。しかしこれに先立つこと数十年前、学生時代に友人の誘いでドン・ジュアンという喜劇をみる機会があった。この日はなぜか時折そのことを思い出しながらのオペラ観劇となった。ドン・ジュアンはフランスのモリエールの喜劇であるが、どちらも石像に招かれて最後を遂げる好色漢の話である。よく似たストーリイであるが、西欧にはドンファン伝説というものがあるらしく、彼らは根っこで繋がっているようである。
その演劇は、コメデイフランセーズの来日公演で、「最も正統的なフランス語」を聞くために行ったようなもの。仏文をかじり始めたばかりの自分にとっては流儷にひびくフランス語の響きと演技の切れのようなものに感じ入りながらただみていただけだった…ということを思い出す。最後は主人を失い、食いぶちをなくした従者スガナレルの『俺の給料!』だったのはよく覚えている。
ドン・ジョバンニ、ドン・ジュアンは、いずれもスペインに発生した好色な悪漢であるドン・ファンの伝説をもとに作られた作品それぞれの国の呼び名である。
原典となった作品は最初にスペインの修道僧が作ったもので、典型的な教会劇であり道徳・宗教色が強かったようだが、イタリアで様々な味つけをなされ、フランスへ渡り、モリエールにより文学的な傑作となったとされる。それから約一世紀を経てダ・ポンテの脚本に
モ−ツァルトが作曲したものがオペラ、ドン・ジョバンニである。
モリエール版のプレイボーイはオペラの主人公とは違って実に多様性を持つ。
貴族出身者の自己中心的な性格は共通するが、女性へのアタックはことごとく失敗(劇中では)する一方、暴漢に教われた貴族に助っ人として加わり、これを追い払うという英雄的行為も行う。
全ての人間の敵としてのワルぶりを表したというよりも、多面的な人間性を与えられたと思ってもいいかもしれない。時代はルイ14世統治下のパリ。宗教上の制約も多かったろうし、漁色家一筋のキャラクターを描かなかったのは公演の危機を考えたためかもしれない。世間の賛同を得るためには貴族社会の風刺が必要であり、従者スガナレルの直面する喜劇(悲劇?)は「給料」がなくなるという現実なのである。
一方オペラにおいては、ドンジョバンニは反省なき悪行に対する神からの報復という伏線の少ない筋書きとなっている。
ここでは主人公に多面的な要素はなく、潔いピカレスクロマン一色である。オペラのほうが120年以上新しいのである。この主人公を徹底した悪漢として表現できた社会風潮は、モリエールの時代よりある意味で「近代的」な時代(モリエールは1665年初演)であったためかもしれない。
かたや音楽がついているのに両者の筋書を比較することもないだろうが、悲しみや嘆き、怒りや恐怖、畏敬の念まで歌と演奏、演技で表現するオペラはやはり素晴らしいものだと思う。芸術作品として最高傑作とされながら庶民的な目線でも流儷なアリアを楽しめるという大衆性も備えており、モ−ツァルトの音楽作品には本当に真の幅があるように思う。
縁を感じる2作品の比較はこのくらいとして、レポートの後半はこのたび接する機会を得たバレンボイム指揮のベルリン国立歌劇場のオペラ公演についての報告としたい。
バレンボイムは今年65歳というが、実に若々しく精力的であり、その指揮ぶりは無縫ともいえる細やかな緩急で我々を翻弄し、興奮の起伏に身を委ねさせる。かつてはモ−ツァルトの再来とまで言われた神童ピアニストとして注目され、晩年のフルトヴェングラーに十代でその才能を認められ、彼のザルツブルグでのドン・ジョバンニのリハーサルに立ち会うことを許されたというほどである。
また、彼が指揮した最初のオペラはザルツブルク音楽祭でのドン・ジョバンニというし、確かに4階席から見下ろすと彼の前にはスコアがなく、暗譜で臨んでいる。彼の十八番なのだろう。この指揮者にこのオーケストラとソリスト達。われわれには最高の音楽を味わうことができる条件がすべて揃っているというわけである。
ベルリン国立歌劇場という伝統が育んだ世界最高峰のアンサンブルが、天才と謳われた指揮者により細部まで完全にコントロールされ演奏する音楽は、一瞬一瞬が素晴らしいの一言である。とても月並みな表現になってしまうが、しようがない。それぞれが贅沢な感じがして、すぐ消えてなくなることが非常にもったいないのである。通であればこの後に延々と、誰のドン・ジョバンニがよかったのエルビーラが巧かった、レポルロは…と続くところである。悲しいかなソリストはすべて私の知らない方々。しかし、ドン・ジョバンニを歌ったペーター・マッテイは若々しくもなかなかの悪党ぶりと良質な声、スケール感もありとても素晴らしかった。ドンナ・アンナはアンナ・サムイルというスラブっぽい美形で声量があり、父親を殺された悲しみもドン・ジョバンニの正体を見破る時のドラマチックなシーンも見事に演じきっていた。
確かに私が一番印象的だったのはドンナ・アンナのこの場面、「ドン・オッタービオ、私、死んでしまう」の見事な絶望の叫びである。
バレンボイムは思索家であるイブン・サイードとの対談でこのようなクレシェンドを行うにあたり必要な「勇気」について話している。音は自然には消えていくものであり、音楽はその自然の法則を拒絶するものである。従って音楽をつくる行為というのは勇気ある行為なのだと。このことは、別にTV放映されたベートーヴェンのピアノソナタの公開レッスンにおいても同様な説明や指導を行っていて印象的であった。ドンナ・アンナのアンナ・サムイルまさに相当の決意を持って非常に息の長い完璧なフォルテイシモをやってのけ、我々はその素晴らしさに息を飲むのだった。
楽しいエピソードを3つ。
1.演奏会の前には必ず流れる携帯にマナーモードをお願いするアナウンス。ひととおり終わったところで絶妙なタイミングでチェンバロが終わりを示す和音。粋なサービスに観客席からこの日最初の拍手がわき起こった。
2.2部の幕間に、突然会場に歓声と拍手が起こり見ると2階席に小泉前総理が着席。私のいる4階席を始め、オペラグラスはみなその方向へ。やや騒然となったが間もなく幕も開いてオペラのスリリングな展開に再び観客は引き込まれていくのだった。
3.後半の食卓を準備する場面はよく余興(?)が入る場面らしいが、なんと指揮者自らが刺身の船盛りを持ってきてドンジョバンニとレポルロにふるまうという大サービス。ステージに登ったバレンボイムが菜箸で指揮をすると会場は笑いに包まれ舞台はエンデイングに向け大いに盛り上がった。
デモーニッシュとは悪魔的なという意味になろうが、よく演奏ぶりを評価する常套句として使われる。バレンボイムの指揮ぶりは果たしてその形容に結びつくものだったろうか?これより前に見たTV放送でのベートーベンの『熱情』を公開レッスンしている風景では理性的で調和、秩序を重視する指導であった。意図的というが一見激情にかられ、早いテンポとヒステリックなクレシェンドなどでオーケストラをインスパイアしたかつてのフルトヴェングラーのような指揮者ではないように思われ、テンポは普通であり、仕上がりは上品かつ明確で美しい音楽だったと思う。
ドンジョバンニは悪漢。その相手となる女性はみなこのオペラにおいて悲劇の対象であり、弱気もの、としてみるのは間違いのようで、これら3人の女性が貞淑さを持ちながらも悪への誘いにも応じて(ぎりぎりセーフの場合もあるが)いるように、デモーニッシュな個体としてみるべきなのは、それぞれに純真さと官能性を内部に混在し醸成した彼女たちなのかもしれない。このような女性は「皆こうしたもの」だという定義はこの時代の風潮なのか、モーツアルトの女性観なのか、貞淑と奔放の間を紙一重でいかようにもたちまわるたくましい女性像に、当時の女性観客も快哉をあげた作品だったにちがいない。
現在はデーモンは至る所に意匠を変えて存在するが、18世紀のオペラにおいて、すでにすべての登場人物のなかに潜むデモーニッシュな部分の存在を、音楽を心理描写の手段として効果的に観客にその存在を意識させたモ−ツァルトは、さらに強烈なデーモンを飼いならしていたのであろうか。
了